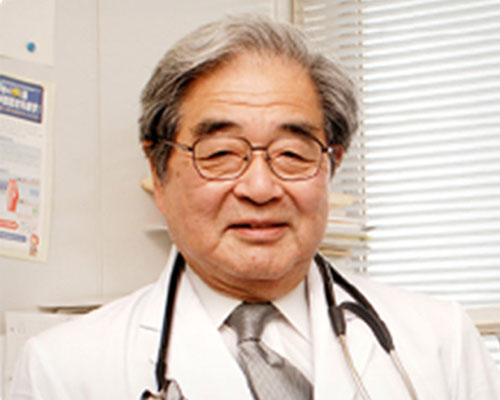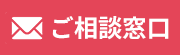習慣が“試験に強い脳”をつくる― 教育現場で活かせる試験準備の脳科学 ―

学校教育において、試験は学習成果を測る重要な機会です。
児童・生徒にとっては日々の学びを形にする場であり、教員にとっては指導の方向性を確認する貴重な機会でもあります。
しかし、どんなに知識を身につけていても、本番で力を発揮できない子どもが多いのも現実です。その原因の一つは、「脳の働き」を理解しないまま、学習・生活リズムが作られてしまっていることにあります。
脳科学の観点から見ると、試験本番で最大限の能力を発揮するためには、日常的な習慣化が不可欠 です。
以下では、教育現場で生徒に指導できる“脳に基づく試験準備法”をご紹介します。
1. 規則正しい生活で、記憶の定着を支える

脳が最も活発に働くのは、安定した生活リズムの中にあります。
睡眠や食事の時間が不規則になると、脳の情報処理能力が低下し、記憶の定着率も下がります。
試験前だけ夜更かしして詰め込む「一夜漬け」は、一時的な短期記憶に依存するため、長期記憶として残りにくいのです。
教育現場では、次のような習慣づけを指導すると効果的です:
-
毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
-
試験開始時刻と同じ時間帯に学習を始める
このように 脳の活動リズムを一定化させることで、試験当日も自然と脳が“覚醒状態を保つ” ようになります。
生徒に「試験に強くなる生活リズム」を意識させる指導が、結果的に学力の安定につながります。
2. 試験形式に応じて脳を“慣らす”

脳は「インプット(読む・聞く)」よりも「アウトプット(書く・答える)」のときに強く活性化します。
そのため、参考書を眺めるだけでなく、実際に 記述式・選択式などの出題形式に合わせた問題演習を繰り返す ことが重要です。
例えば、記述式問題では自分の言葉で説明する過程で前頭前野が活発に働き、論理的思考と記憶の結びつきが強化されます。
一方、選択式問題では瞬時の判断や情報検索が求められ、ワーキングメモリーの鍛錬につながります。
教員としては、生徒が受ける試験形式に合わせて「脳が慣れる練習」を計画的に取り入れることが望ましいでしょう。
3. 実技試験・運動では「ミラーニューロン」を活かす

技能や実技を伴う科目では、脳と身体の協調が重要です。
脳科学研究では、人の動作を見ただけで自分の脳がその動きをシミュレーションする「ミラーニューロン」の働きが明らかになっています。
つまり、上手な人の動きを観察するだけでも脳内で学習が始まっている のです。
授業や部活動では、手本を見せる指導の意義を再認識する必要があります。
加えて、観察 → 模倣 → 練習 のサイクルを繰り返すことで、神経回路のつながりが強化され、技能習得が加速します。
まとめ:「習慣化」がもたらす脳の最適化
脳は“変化を嫌う臓器”といわれますが、同時に“習慣によって強化される臓器”でもあります。
毎日同じ時間に学習を始める・一定のリズムで休憩を取る・試験形式に合わせて練習する──こうした習慣の積み重ねが、脳を試験に最適化された状態に導く のです。
試験対策を単なる「暗記指導」で終わらせず、脳の仕組みに基づいた学習習慣の形成 へと導くこと。
これが、これからの教育における重要な視点です。
規則正しい生活、試験形式への慣れ、観察と練習のサイクル──これらを教員が意識的に促すことで、生徒たちは自然に“試験に強い脳”を育てることができます。
生徒一人ひとりが「脳が働きやすい環境」を自分で整えられるよう支援することも、教員に求められる学習支援のかたちといえるでしょう。
Kubotaのうけん創始者
久保田 競 (くぼた きそう)
1932~2024年、大阪出身。京都大学名誉教授、医学博士、脳科学者。東京大学医学部・同大大学院卒業。京都大教授、同研究所所長を歴任。2011年春、瑞宝中綬章を受賞。40年以上前から赤ちゃん育脳の意義を唱え続け、妻カヨ子氏とともにくぼた式育児法を考案。「脳の発達に応じた教育」をいち早く提案してきた。