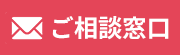受験生が「眠れない」原因は生活習慣にあり。今日からできる4つの見直しポイント
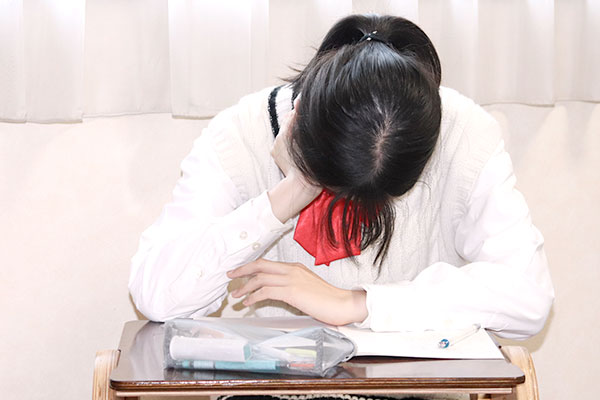
眠れない受験生の共通項4つ
受験期を迎える生徒の中には、「脳が疲れているのに眠れない」「眠っても熟睡できず、翌朝まで疲れが残っている」といった悩みを抱えている子が少なくありません。一見、勉強のしすぎや緊張によるもののように思えますが、これらの受験生に共通しているのが、下記の4つ。
- 座っているばかりで運動はほとんどしない
- コーヒーを時間構わず多く飲む
- 寝る前に夕食をドカ食いする
- 寝る前にスマートフォンを見る
このように、眠れない背景には、日々の生活習慣に原因が潜んでいるのです。
では、それぞれの解決策を見ていきましょう。
①運動不足
日中の運動は心地よい体の疲労を生み、夜の眠気を誘います。
睡眠の質を高める効果が期待できる運動強度は、息が弾み汗をかく程度です。ウォーキングや軽い筋力トレーニング、掃除機をかける、階段を昇るなどの活動があげられます。
運動する時間は1日1時間が望ましいですが、そんなに時間が取れない場合は30分でもよいでしょう。とにかく、日常に運動を取り入れる習慣づけが大切です。
→階段を使うなど、日常に適度な運動を取り入れる
②カフェインの過剰摂取
カフェインとは、コーヒー豆・茶葉・カカオ等、天然の食品に含まれる成分の1つです。これらを原料にしたコーヒーやお茶、エナジードリンクに、カフェインは多く含まれています。
カフェインは、頭が冴え、眠気を覚ます効果が多くの人に知られていますが、カフェインの覚せい作用はあなどれません。
また、カフェインを毎日摂取していると体が慣れてしまい、摂取しないと眠気や疲れを感じたり、集中力が続かない状態になることも。カフェインの感受性には個人差がありますが、コーヒーの場合飲むなら1日3杯までが無難です。また、コーヒーを飲むのは就寝4時間前までとし、どうしても飲みたい場合はカフェインレスを選びましょう。
→コーヒーは1日3杯まで。飲むのは遅くとも寝る4時間前までに
③寝る前のドカ食い
夕食の時間を惜しんで勉強し、帰宅後ドカ食い、ベッドへ直行…これは、眠れない人の典型的な生活スタイル。就寝前の食事は、睡眠の質や健康に大きく関わる要素です。満腹状態だと、消化活動のために胃は働き続けるため、なかなか寝つけないのです。理想は就寝前3時間の食事を避けることですが、難しい場合は、体に負担の少ない低カロリーで消化に良い食べ物を、少量だけ食べるようにしましょう。19時ころにおにぎりなどの間食をとっておくと、帰宅後のドカ食いを防ぐことができるのでおすすめです。
→夕食は就寝 3 時間前までに。どうしても遅くなる場合は、間食をとって帰宅後のドカ食いを防止する
④布団の中でのスマホチェック
寝る前に新しい情報を脳に送ると、脳が目覚めて興奮状態になります。また、スマートフォンの画面から発せられる青色の光は、脳を興奮させる効果が強いことがわかっています。
休憩時間以外は電源を切る、スマホを寝室に持ち込まないなど、強い意志をもってルールを決めましょう。スマホに触らずに眠りについた日と、ダラダラとSNSを見続けた日とでは、眠りの質も、翌朝の集中力もまるで違うことに気づくはずです。
→休憩時間以外は電源を切る、スマホを寝室に持ち込まないなど、ルールを決める
まとめ:眠りの質を見直して、学習効果を高めよう
「眠れない」「眠りが浅い」と悩む受験生は少なくありません。実はその原因、多くは生活習慣の乱れにあります。勉強時間を確保するあまり、睡眠の質を下げてしまっては、本来の学習効率も落ちてしまう恐れがあります。
まず見直したいの運動不足は、軽いウォーキングや階段の昇降など、日常生活の中に適度な運動習慣を取り入れることで、睡眠の質を高める効果が期待できます。
次に重要なのが、カフェインの摂取量とタイミング。コーヒーは1日3杯までとし、就寝の4時間前以降の摂取は控えるのが理想です。
さらに、受験生に多いのが夜遅くのドカ食い。夕食は就寝3時間前までに済ませるか、間食で空腹を軽く満たしておくと、ドカ食いを防げます。
そして、現代の受験生にとって最も大きな落とし穴がスマートフォンの使用です。寝る直前までSNSや動画を見続けるやブルーライトの影響で、脳が覚醒し、眠りに入りにくくなります。スマホは寝室に持ち込まない、就寝1時間前には使用を控えるといったルール作りが有効です。
良質な睡眠は、記憶の定着・集中力の維持・メンタルの安定に欠かせないもの。勉強の質を高めるためには、まず「眠れる環境」を整えることが必要不可欠です。今回紹介した4つの生活習慣の見直しポイントを、今日から少しずつ取り入れてみましょう。
「城南医志塾」顧問医師
医師・医学博士・経営学修士(MD・Ph.D・MBA)
裵 英洙 (はい えいしゅ)
1972年奈良県生まれ。かつては外科医として胸部手術を中心とした診療に従事。現在は「ハイズ株式会社」代表取締役として勤務する傍ら、臨床医として医療現場に携わる。著書に「なぜ、一流の人は「疲れ」を翌日に持ち越さないのか」「医療職が部下を持ったら読む本」など多数。