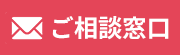子どもも乱れる「自律神経」のととのえ方

子どものストレスが深刻化している
文部科学省の2023年度調査によると、不登校の状態にある小中学生は34万人余り。11年連続で増加が続き、過去最多を更新しました。不登校の1番の原因は「無気力・不安」によるもので、全体の55%を占めていますが、これは2番目の原因である「学業不振」の15%を大きく引き離しています。なぜ、このような子どもが増えているのでしょうか?
国立成育医療研究センター2022年に発表した調査によると、中等度以上のうつ症状がある子どもの割合が、高校生24%、中学生22%、小学4〜6年生10%にのぼることが明らかになりました。微熱やだるさ、腹痛などの体調不良や、寝起きの悪さや無気力などを訴える子ども、不登校の子どもが増えているのは、子どもたちの不安やストレスが深刻化していることの現れです。これらは、「自律神経の乱れ」が原因である可能性が考えられます。慢性的な不安やストレスを抱えていると、自律神経の乱れを引き起こし、それが心身の不調の原因となるのです。
自律神経の乱れが引き起こす症状

「自律神経」ってなに?
「自律神経」は、人間の体に張り巡らされている神経の一部で、「交感神経」と「副交感神経」から成ります。「交感神経」は日中起きているときや緊張しているときに優位になる神経で、「副交感神経」は心身をリラックス状態にして休息させる神経です。この二つの神経は互いにバランスを取りながら、血管や内臓などをコントロールして体を良い状態に保っています。しかし過度なストレスや不規則な生活習慣、急激な気温の変化などによってバランスが乱れると、さまざまな不調が現れることがあるのです。
子どもにも見られる「自律神経の乱れ」
夏や冬など気温の変化が大きい時期に、「なんとなく不調を感じる」という人は多くいます。特にここ数年の夏は、40度近くまで気温が上がるなど猛暑日が続くことが多く、寒暖差や気圧の変動に疲労がたまりやすくなっています。実はその不調は、大人だけではなく子どもも感じているのです。
特に気を付けたいのが、夏休みや冬休みなどの長期休暇明け。なぜなら、自律神経は生活リズムが変わることで乱れやすくなるからです。自律神経が乱れると、「やる気がでない」「疲れやすい」「気が散漫になる」「不安になる」などの症状が現れます。休み明けに登校を渋り、そのまま不登校になってしまう子どもは少なくないですが、自律神経の乱れが影響している可能性は大いにあります。自律神経の乱れを放置しておくと、学校生活に支障をきたす恐れがあるので、注意が必要です。
専門家監修“自律神経ととのえメソッド”4選!
では、自律神経の乱れはどうしたら防げるのでしょうか? 自律神経のバランスを整えるためには、まずはストレス解消を心掛け、生活リズムを整えることが重要です。ここでは、専門家である石原先生監修の“自律神経ととのえメソッド”を紹介します。今日からすぐにできるメソッドなので、ぜひ生徒にも教えて、自律神経の乱れを防いで前向きに学校生活を送れるようサポートしてあげてください。
1.入浴をする
暑い夏や忙しい日は簡単にシャワーで済ませがちですが、心身を休めるためにはやはり入浴がお勧めです。入浴することで「副交感神経」を高めることができます。効果的な入浴法は、寝る時間の1〜2時間前に、40℃くらいの少しぬるめのお湯に浸かることです。あまり熱いお風呂に浸かってしまうと、交感神経が高くなり、身体が興奮状態になってしまうので気をつけてください。意識的に湯船に浸かり、心身ともにリラックスさせましょう。

2.ストレッチやマッサージをする
自律神経の乱れを抑えるためには、マッサージとストレッチもおすすめです。全身の血のめぐりが良くなることで、身体が整います。入浴後は体が温まっていますから、より効果的です。首や肩を回したり、伸ばしたり、手軽なストレッチであれば、勉強中でも気軽に行えます。ぜひ試してほしいのが、「足の指を開くだけ」の超簡単ストレッチ。ふくらはぎなど足全体の筋肉に効きます。

3.寝る前にスマホから離れリラックスする時間をとる
寝室の電気を消した後、寝る直前までスマホをいじってしまう生徒は多いと思います。寝る前にスマホの明るいが画面を見ていると、夜なのに交感神経が活性化されてしまい、自律神経の乱れを引き起こしてしまいます。寝つきが悪くなるなど睡眠の質が落ちると、成長ホルモンの分泌にも影響します。寝る1時間前までには、スマホを見ることをやめさせましょう。

4.「歩行」や「噛む」などリズム運動を行う
自律神経を整える方法として、リズム運動が良いことがわかっています。リズム運動には「呼吸」、「ウォーキング」、「サイクリング」、「噛むこと」などがあります。ガムは、「噛む」ツールとして日常生活の中でリズム運動を取り入れやすくなるのでおすすめです。また、「ガムを噛むこと」で、集中力の向上や自律神経が整うなど、さまざまないい機能があることもわかっています。

まとめ
自律神経は、人間の体に張り巡らされている神経の一部で、交感神経と副交感神経から成ります。この二つの神経は、互いにバランスを取りながら体を良い状態に保っていますが、ストレスや不規則な生活習慣、急激な気温の変化などによってバランスが乱れると、さまざまな不調を引き起こすことがあります。
自律神経の乱れは大人に限ったことではなく、子どもにも起こることです。子どもたちの不安やストレスが深刻化し、不登校の子どもが増えていますが、これは「自律神経の乱れ」が原因である可能性が考えられます。慢性的な不安やストレスを抱えていると、自律神経の乱れを引き起こし、それが心身の不調の原因となるのです。
自律神経のバランスを整えるためには、まずはストレス解消を心掛け、生活リズムを整えることが重要です。気軽に毎日の生活に取り入れられる“自律神経ととのえメソッド”を試すなど、できるところから改善していきましょう。
“自律神経ととのえメソッド”監修
イシハラクリニック医師 石原新菜先生

医師・イシハラクリニック副院長 ヒポクラティック・サナトリウム副施設長
健康ソムリエ理事ロングライフラボ理事
2000年4月帝京大学医学部に入学。
2006年3月卒業、同大学病院で2年間の研修医を経て、現在父、石原結實のクリニックで主に漢方医学、自然療法、食事療法により、種々の病気の治療にあたっている。